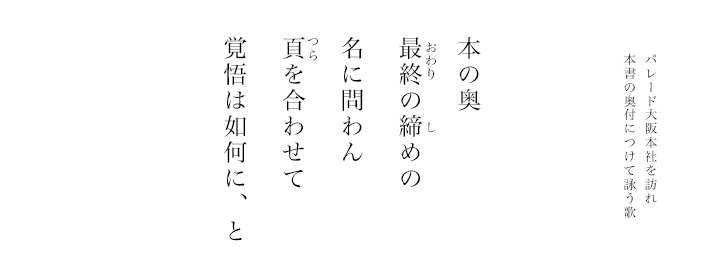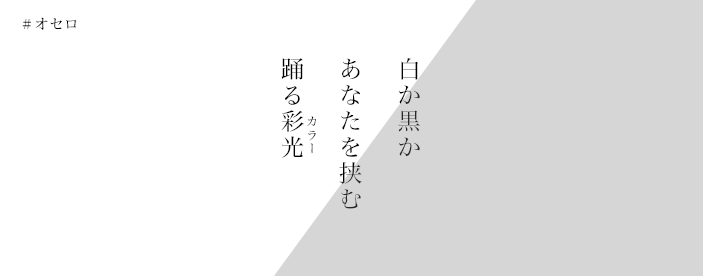
自由とは、なんとでっかいものだ。 自由のこっち端から自由の向こう端へやっとこ辿り着いたら、
おやまあ、元いた自由ってとこが山の先き遥か彼方じゃないか。
三月二十六日 パレード大阪本社
文学の歴史を鑑みると、「言論の自由を守り、己の感性を貫く。」
このことは、命と名誉を賭けた人生行為であった。
島流しにあった歌人、戦中に投獄された文学者。
一転して戦後に戦犯だと糾弾された詩人たち。
常に泥をかけられ、刃を向けられながら進む。
いざ出陣したら、味方に背後から撃たれる。退路を断たれる。
これは、数々の戦史に記されていることでもある。
- 死んでしまったら、人のせいにもできやしない。-
私はこのことを、一個の身体表現に置き換えて自問してみる。
私が跳躍した瞬間、無風夢中の意識が地上の何処と繋がっているのか。
着地する地面は柔かな芝生か。それとも薄氷の沼か。茨の絨毯か。
そもそも、踏ん張れないほど地面は泥濘んでいないか。
地上の守人(もりびと)と私はしっかり結ばれているのか。
いや、自費出版の場合、その確認も十分にされずに出版される。
殊に本書は全て自分の手による高純度な作品。元より放り投げただけの矢のようなもの。
おまけに、いつまでも本の最後にやりきれない異物感が残っていた。
流通の慣例として、本の最終ページ(奥付)に発行人として出版社の代表名を刻まなくてはならなかったのだ。
結局、見も知らぬ男の名を、私自身で私の身体(本書)に打ち込んだ。
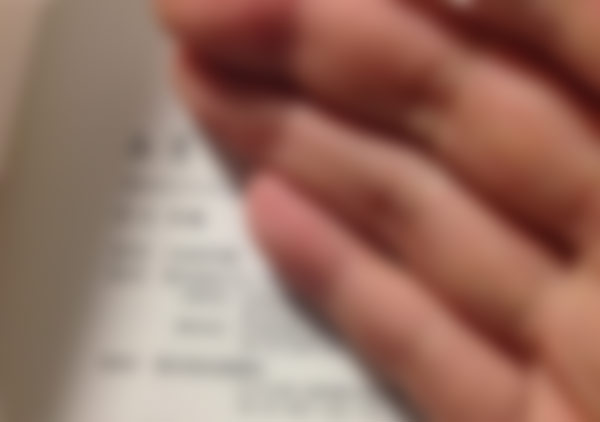
私は本を保証するため、所在と名をお借りすることにした。
彼らにしてみれば、私こそ純粋な異物であり、宿を借る虫のごとく。
まさに純粋な異物である私は、見通しの悪い水面下で、詮索や妨害、冷やかし行為を受け続けていたに違いない。
心当たりは一年分。吹きっさらしの私の心は安まる時がなかった。
そんな過酷な状況だからこそ、人との繋がりが美しく思えることがあった。
去年の夏頃から私は祈っていたのかもしれない。
それでも、いつまでも危険でぐらぐらな地上は固まらなかった。
私は「檸檬」を期に、初めて本社の社長を訪れることにした。
本書は、経営者の視点では及ばない範疇に存在する集中体なので、
会ったら多少がっかりすることはわかっていた。
午前十時、黒塗りの鮮烈。
色々と気使いを頂き、楽しくお話させて頂いた中「言論の自由を守るため」との言葉が一番残った。
彼の意味するところは、私の知る現実と乖離していた。
一般的に、お客様の自由を守るために言葉を発しない。
気になっていたとしても、見て見ぬ振りをして直接関わらない。
間口を広げ過ぎて冷ややかになったビジネスマナーを言っているような気がしてならなかった。
面すれど、私の意味と交わることがなかった。
瞬間、私は互いの距離(淵)を見ることができた。 現実を認めた。
でも例え彼の自由が軽いビジネストークだとしても、前向きなメッセージであることは確かだ。
一歩づつ歩み寄ることが大事なのかもしれない。
前日、二十五日に訪れた「檸檬」梶井基次郎の墓は、ここから三駅しか離れていなかった。
その日は、思いつくまま堺まで足を伸ばし、仁徳天皇陵をぐるりと廻った。
次の日、社長は堺に住んでいたことを聞く。 昔、義父は堺で働いていた。
知りながら初対面となるスタッフの方々とも挨拶をした後、秀吉が子孫のために築いた大阪城へ登った。
天守の高みから昨日の古墳を重ねて考えた。
巨大すぎる建造物は、きっと子孫のための祈りなのだろう。
 仁徳天皇陵 |
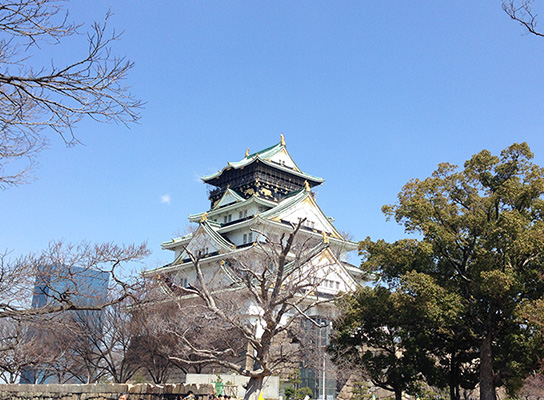 大阪城 |
|
|